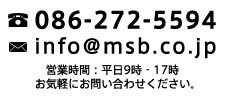備前焼の大甕について(2010年4月号)
宮下酒造株式会社
社長 宮下附一竜
室町中期から戦国時代に高い評価を受けた「天野酒」は、河内長野市天野町の天野山金剛寺で造られた僧坊酒ですが、このお寺には三石入りの古い備前焼の大甕が残っています。おそらく酒の仕込甕として使われたと思われますが、室町後期には西日本各地に備前焼が瀬戸内の海運を利用して広く流通していたと考えられます。
備前焼の起源は、六世紀後半より備前国古代邑久郡で生産されていた須恵器に求められる陶器です。12世紀には原料となる土や燃料に恵まれた備前市伊部周辺部の山麓で窯業が始まり、鎌倉時代後期には窯が熊山山上に築かれ、窯の傾斜が強くなり、焼成温度も高くなったために、茶褐色に固く焼き締められた壺・擂鉢・甕の三器種が量産されるようになったようです。南北朝末期ごろと推測される水の子岩沈船遺跡からは、約180個体にのぼる備前焼の壺・擂鉢・甕が引き上げられています。
室町時代になると、窯は山麓に下り、その規模は長さ四十メートルに及ぶ大型となり、各地の遺跡からの出土量も膨大なものとなっています。
このように実用の器として地位を確立した備前焼ですが、室町後期に流行を見せ始める侘び茶の世界において、村田珠光・武野紹鴎・千利休に取り上げられるようになり、茶陶として水指・花生などが注目を集めるようになりました。
一方、室町中期になると、10石以上の大型木桶が出現し、酒造容器は甕から大型木桶に移り、酒仕込の単位が大きくなっていきました。大型木桶を作るのに必要な製材用大鋸(おが)は十四世紀末から十五世紀、表面や側面を仕上げる台鉋(だいかんな)は十五世紀中頃に中国か朝鮮より渡来したといわれています。こうして中世日本の木工技術の革新が、近世酒造業の発展に寄与することになっていくことになったのです。