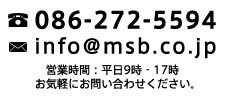2015年6月21日日曜日 読売新聞 酒蔵探訪@宮下酒造 蓋麹 夜通し守る
酒造りは「一麹(こうじ)、二もと、三造り」と言われている。酒米のでんぷんを糖に変える麹の出来が、酒の味を左右するからだ。
酒蔵には「室(むろ)」と呼ばれる部屋がある。最適な室温と湿度の中で、質の良い麹は生まれる。機械製造が普及しているとはいえ、今も人の手によって丹念に造られている。
「製麹(せいぎく)」と呼ばれる製造で、最も手間のかかる「蓋麹法」を守り続ける宮下酒造(岡山市中区西川原)を訪ねた。
蒸した米に麹菌を振りかけ、小分けして蓋(木箱)に盛っていく。小さいものから「蓋麹」「箱麹」「床麹」と製法の呼び名が異なる。蓋麹だとA3サイズほどで、同社の室には多い時で約50個積み上げられる。
室の内部は温度と湿度が一定に保たれている。とはいえ、場所によって微妙に異なる。全ての蓋が同一条件になるよう、2~3時間ごとに蓋を上下左右入れ替えなければならない。
「夜通し見守っていなければならないが、そうすることで麹が米粒の奥にまで浸透し、雑味がなく、香りの高い酒に仕上がる」。専務の宮下晃一(37)は説明する。手間がかかるだけに、この製法の麹は、大吟醸や純米大吟醸といった高級酒の仕込みに使用されている。
創業は1915年。67年に玉野市から現在地の本社に蔵を移した。近くには日本名水百選の「雄町の冷泉」があり、「幻の酒米」と称される雄町米が栽培されている。それらを原料にした「極聖(きわみひじり)」などの銘柄は、やや辛口。全国新酒鑑評会では、県内最多の金賞18回を誇る。
長年、味を支えたのが備中杜氏(とうじ)の中浜昭夫。備中杜氏組合連合会長を務め、「現代の名工」にも選ばれた。現在は若手社員が技とともに、伝統を守り続ける。薫陶を受けた製造部長の岡崎達郎(たつお)(37)も「丁寧に原料を処理することが、良い酒を造る最初の一歩」と基本姿勢を崩さない。
夏が過ぎ、秋の到来とともに仕込みの季節となる。毎年、蔵の入り口に中浜がこしらえた神棚に手を合わせ、酒の出来を祈願することから作業は始まる。
年を越し、大吟醸の仕込みが始まった時、作業を終える「こしき倒し」の儀式の時も、従業員は神棚の前に並ぶ。宮下は語る。「節目、節目に、良いお酒ができますようにと全員でお祈りしている。酒の神様はやっぱりいると思う」(敬称略)